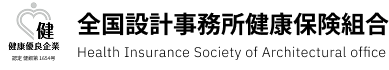よくあるご質問
設計けんぽについて
「任意継続被保険者資格取得申出書」および「健康保険任意継続被保険者給付金受領金融機関指定(変更)届」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合へ提出してください。
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書をご提出ください。申出書が当組合に届いた月の翌月1日が資格喪失日です。
(例:申出書4/30着→資格喪失日5/1。申出書5/1着→資格喪失日6/1)
発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。
資格情報のお知らせはマイナンバーの紐づけが完了した全員に発送され、資格確認書は健康保険証の代わりとしてマイナ保険証のない方に発行いたします。
当組合でマイナンバーの登録を行った4営業日後を目安に、マイナンバーの紐づけが完了した方から随時発送いたします。人によっては過去の健康保険加入状況等により、マイナンバーの紐づけに時間を要する場合があります。
使わなければ組合にご返却ください。有効期限が切れた場合は破棄してください。
メールアドレスの入力誤りもしくは、ご使用されているメールアドレスのドメイン設定の影響が考えられます。特定のメールアドレス以外を受信拒否する設定になってないかなど、ご確認をお願いいたします。もしくは別のメールアドレスでのご登録をお試しください。
担当者として追加が可能です。責任者アカウントをご登録の上、ログインしていただき、事業所名の横のⅴマークを押下すると表示される事業所担当者一覧から手続きができます。
ログインしていただいた後、登録名の横のⅴマークを押下すると表示される、アカウント情報変更から手続きができます。
通常、責任者を変更する場合は責任者アカウントでログインしていただいた上で、変更する形となります。責任者アカウントでログインできない場合は再登録が必要になるため、再度初期ログイン情報をお送りしますのでお問い合わせください。
加入
試用期間というのは、一般に採用した人の健康、成績、能力など正従業員としての適格性をみるために設けるものであり、その限りでは臨時に使用されるのではなく、また期間を定めて雇用されるものでもないことから、適用除外には該当せず、入社の当初から被保険者の資格を取得させなければなりません。
会社役員の健康保険の適用については、常勤非常勤問わず、法人から労務の対象として報酬を受けており、「使用される者」と判断される場合は、被保険者の資格を取得するものとされています。なお、嘱託についても事実上の使用関係があると認められる限り一般の従業員と同様に取り扱うべきものと考えられます。
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決められます。なお、資格取得届を提出する際には見込み残業代も含めた額で届け出ることになりますので注意が必要です。
-
月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
-
日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
被扶養者異動届に、以下を添付してご提出ください。
-
入籍日の記載があるもの(婚姻受理証明書原本または戸籍謄本原本)
-
配偶者の収入確認書類(無職の方は非課税証明書原本、お勤めの方は源泉徴収票の写し、最近お勤めされた方は雇用契約書の写し)
-
年金の振込通知書の写し(年金を受給している場合)
届出を行う時から先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円を超えていたとしてもその実績から判断するのではなく、前年の収入を参考にしながら、届出を行う時から先1年間の見込み収入が130万円を超えるかどうかによって判断することになります。
保険料は被扶養者のある、なしには関わらず、被保険者の標準報酬月額によって決められています。被扶養者の人数が増減しても変わりません。
証明書類は原則、写しでの受付は行っておりません。原本をご提出ください。
なお、下記の書類につきましては、写しでの受理を行っております。
-
雇用保険受給資格者証
-
年金振込通知書
-
離職票
-
給与明細
-
雇用契約書
税法上の扶養控除対象者は前年(1月から12月)の年間収入をみますが、健康保険上の扶養認定は、申請時点より今後1年間にどのくらいの収入が見込まれるかで判断します。また、税法上と健康保険上では収入の認定基準も異なっており、健康保険は60歳未満の人は年収130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は180万円未満(月額150,000円未満)が認定基準となりますので、年収(パートタイマー・アルバイトの給与収入等)が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入が1ヶ月あたり108,334円(108,334円×12ヶ月=1,300,008円)以上見込まれるようになった時点で、削除の手続が必要となります。
給与収入は交通費等を含む総収入です。
勤務日数や勤務時間短縮により収入減となりお勤めの会社の社会保険の資格を喪失し、喪失後の給与が被扶養者の金額の範囲内(交通費等を含む総支給額が60歳未満月額108,334円、60歳以上月額150,000円未満であり、かつ被保険者の収入の1/2以下であること)になる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」「資格喪失証明書(原本)」「雇用契約書の写し」が必要です。
-
雇用契約書により今後の収入額が被扶養者の範囲内となることが確認できなかったときは追加書類が必要となる場合があります。
【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がある方】
給付制限期間は加入できます。
ただし、受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で被扶養者から外す手続きが必要となります。
【雇用保険の受給開始までの期間(給付制限期間)がない方】
受給日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の方のみ加入できます。
任意継続被保険者の資格を喪失した後に、被扶養者の申請をしてください。
なお、状況によっては被扶養者の申請をしても被扶養者として認定されない場合もあります。その場合は国民健康保険等に加入していただくことになります。
被扶養者の人数にかかわらず、原則として年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の多い人の被扶養者となります。
夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。
主たる生計維持者が被保険者(妻)へ移行しているのであれば、扶養認定は可能です。 ただし、再就職や失業給付金の受給開始等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ異動する必要があります。
-
夫の退職日が分かるもの
-
夫の退職後の収入確認
-
子の資格喪失証明書
その他状況によって添付書類が追加で必要になる場合がございます。
義父母は同居していなければ被扶養者とはなりません。被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者が生計を維持していることが条件になります。したがって、別居している場合には、たとえ生計維持関係があっても被扶養者にとなることはできません。
仕送りしている事実を客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しをしたという証明では認められません。送金の実績が残る(金融機関の振込み証明書、通帳の写し等)方法で仕送りしてください。また、仕送り額は被扶養者の収入を上回っていることが必要です。
税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。遺族年金の受給額が180万円を超えておりますので、被扶養者となることができません。
健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書をご提出ください。申出書が当組合に届いた月の翌月1日が資格喪失日です。
(例:申出書4/30着→資格喪失日5/1。申出書5/1着→資格喪失日6/1)
保険料の算出方法が異なります。国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
任意継続保険の保険料の額は以下の1.2.のいずれか低い方で、事業主負担分がないため全額自己負担となります。
-
退職時の標準報酬月額に対する保険料
-
当組合の全被保険者の前年9月30日現在の標準報酬月額の平均額に対する保険料
できません。金融機関窓口またはATMやインターネットバンキングにて納付してください。
まずは医療機関に任意継続保険の手続き中とご相談ください。全額自己負担した場合は、後日、療養費として請求することができます。
-
任意継続被保険者の資格は、退職日の翌日から継続されますので資格の空白期間はできません。
土日祝日を含めて資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内が申請期限となります。
できません。申請期限の「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」 (天災地変、交通、通信関係のストライキなどによって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は受理できません。
健康保険料の納付期限は翌月末となっており、在職中、毎月の給与から前月分の健康保険料が差し引かれていた場合、最後の給与からは5月分の健康保険料が引かれている可能性がありますので、事業所へご確認ください。6月分からは任意継続被保険者として保険料を納めていただくことになります。
-
健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても、31日加入しても、1か月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。
変わります。任意継続保険の手続き完了後、新しい記号・番号が記載された資格取得通知をお送りいたします。また、マイナンバー並びに氏名・生年月日等の情報がオンライン資格確認システムに問題なくデータ登録完了しましたら、新しい記号・番号が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、マイナ保険証を利用して受診が可能となります。なお、マイナポータルの「健康保険証」画面にて新しい記号・番号が反映されていればその時点でマイナ保険証を利用して受診が可能です。
-
在職時にお使いの健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行されている方のみ)は退職の際事業所へお返しください。
健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。保険料を納付期限までに納付しなかったことにより資格を喪失した場合には、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたしますので、その通知書を持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。なお任意継続保険の健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行されている方のみ)については同封の返信用封筒にて返却してください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。
国民健康保険に入りたい場合はお住まいの市区町村へ、ご家族の扶養に入りたい場合には、お勤めされている方の勤務先を通じて加入している健康保険組合にお問い合わせください。
任意継続保険資格の喪失事由は健康保険法第38条で要件が定められており、以下の喪失事由のいずれかに該当する必要があります。
-
任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき
-
被保険者が死亡したとき
-
保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しなかったとき
-
就職して被保険者となったとき
-
船員保険の被保険者となったとき
-
後期高齢者医療の被保険者となったとき(被保険者が75歳に達したとき)
-
任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
(資格喪失申出書が受理された日の属する月の翌月1日が喪失日となります。)
「国民健康保険に切り替えたい」、「配偶者の被扶養者になりたい」(注)場合には、上記3(保険料未納による喪失)または7(被保険者からの申出による喪失)のいずれかの手続きとなります。
被保険者本人が死亡したときは、その翌日付で喪失となり、以下お手続きが必要となります。
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」に「被保険者の死亡が確認できる書類(死亡診断書写し)」
「任意継続保険の健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(被扶養者分も併せて/いずれも発行されている方のみ)」を添付し当組合へ郵送してください。
死亡喪失のお手続き完了後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を送付いたします。
なお、保険料に還付が生じた場合は、喪失通知書と併せて保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。(法定相続人の確認書類が必要となる場合があります)
被扶養者が死亡したときは被扶養者異動届の提出が必要です。
「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」に
「新しい会社の資格情報のお知らせの写しまたは資格確認書の写し」
「任意継続保険の健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行されている方のみ)」
を当組合までご提出ください。
手続き完了後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を送付いたします。
なお、保険料に還付が生じた場合は、喪失通知書と併せて保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。
事前の手続きは不要です。
当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を送付いたしますので、そちらをお持ちいただき国民健康保険等への切り替えをお願いします。
なお、資格喪失日が土日祝日の場合は翌営業日の発送となります。また、任意継続保険の健康保険証/健康保険高齢受給者証/資格確認書(いずれも発行されている方のみ)につきましては、当組合へ返却してください。
喪失日(納付期日の翌日)から1週間~2週間で登録住所へ送付いたします。
発行されません。マイナ保険証がない方は資格確認書をご利用ください。
資格情報のお知らせはマイナンバーの紐づけが完了した全員に発送され、資格確認書は健康保険証の代わりとしてマイナ保険証のない方に発行いたします。
当組合でマイナンバーの登録を行った4営業日後を目安に、マイナンバーの紐づけが完了した方から随時発送いたします。人によっては過去の健康保険加入状況等により、マイナンバーの紐づけに時間を要する場合があります。
使わなければ組合にご返却ください。有効期限が切れた場合は破棄してください。
まずは、受診する医療機関に健康保険の加入手続き中とご相談ください。全額自己負担した場合は、後日、資格取得日以降の診療分について療養費として請求することができます。なお、健康保険加入手続中の資格証明書の交付は行っておりません。
加入中の出来事
産休に入りましたらご提出ください。
育児休業の取得は女性に限られたものではありません。性別に関わりなくすべての労働者が育児休業を取得できます。ただし、女性に関しては労働基準法に定める出産後56日間(産後休業期間)は、育児休業に当たりませんが、男性は該当します。
育児・介護休業法に定められている子が1歳に達する日までの育児休業、子が1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業、子が1歳6ヶ月から2歳に達するまでの育児休業、1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業、の各休業期間において、それぞれ「健康保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を事業主が育児休業期間中に当組合に提出してください。
1回で行うことはできませんのでそのつど申出書の提出が必要です。育介法において、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達する日において本人又は配偶者が 育児休業をしており、且つ1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合に、本人の申出により認められるものです。また、この育児休業については、事業主の義務とされており、要件を満たした場合は、その申出を拒むことができないことになっています。これらのことにより、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業については、子が1歳に達した時点で本人が申出し、事業主が確認したうえで開始することとなります。そのため、保険料免除の申出についても同様の取扱いとなり、そのつど申出書を提出することになります。
平成29年10月1日育児・介護休業法の改正により、子が1歳6ヶ月から2歳に達する日までの育児休業をしている被保険者についても申出により保険料が免除となります。
被保険者が育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合または終了予定日を延長する場合は、「健康保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を事業主が当組合に提出する必要があります。
また、延長後の終了予定日は、子が1歳に達する日までの育児休業の場合は1歳に達する日、1歳から1歳6ヶ月に達する日までの場合は1歳6ヶ月に達する日、1歳6ヶ月から2歳に達する日までの場合は2歳に達する日、1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業の場合は3歳に達する日をそれぞれの限度としています。
月額保険料については、月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは育児休業開始日と終了日が同月内の場合で14日以上の育児休業等を取得した場合は当該月の保険料が免除となります。なお、賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料免除の対象となるため、育児休業開始日と終了日が同月内の場合は賞与に係る保険料は免除となりません。
証明書の添付は不要です。健康保険証または資格確認書をお持ちの場合は、健康保険被保険者氏名変更(訂正)届に添付してご郵送ください。
必要ありません。
健康保険被保険者氏名変更(訂正)届を連名でご記入ください。
健康保険住所変更届をご提出ください。
住民票に変更があれば健康保険住所変更届をご記入ください。
資格確認書等の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができます。
なお住所を変更した場合は、「健康保険住所変更届」を事業主を通じてすみやかに当組合に届け出てください。
資格確認書等はクレジットカード等と異なり、使用を停止することはできません。資格確認書等が盗難等にあった場合は、早急に警察に届け出てください。当組合へは、会社の事業主を経由して(任意継続被保険者である場合は直接健保へ)「資格確認書再交付申請書」に「資格確認書滅失届」を添えて提出してください。
脱退・資格喪失
「任意継続被保険者資格取得申出書」および「健康保険任意継続被保険者給付金受領金融機関指定(変更)届」を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合へ提出してください。
退職すると被保険者の資格を失います。健康保険証につきましては、経過措置期間が令和7年12月1日までとされており、この期間内に資格を喪失した場合は健康保険証を事業主経由で当組合に返却してください。資格確認書につきましては、有効期間内に資格を喪失した場合は事業主経由で当組合に返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。なお事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「健康保険被保険者資格喪失届」に回収した資格確認書等を添付して提出する義務があります。
「健康保険 資格喪失証明願」を当組合にご提出いただくことで、「資格喪失証明書」を交付することができます。
申請書をダウンロードいただき、事業主を経由せずに直接、当組合宛にご提出ください。
被扶養者の方の資格証明も必要な場合は、「被扶養者の氏名」欄を記載し、ご提出ください。
当組合にて内容確認後、「資格喪失証明書」を作成し、申請書に記入された住所にご郵送いたします。
被扶養者である家族が就職、離婚、死亡した場合など被扶養者でなくなったときは、被扶養者の削除の手続きが必要です。「健康保険被扶養者(異動)届」に交付を受けているときは、健康保険証・健康保険高齢受給者証・資格確認書を添付して事業所を経由して当組合に提出してください。
パートタイマー先で健康保険に加入した場合は、当組合の被扶養者から外れることになります。
また、健保に加入していない場合でも収入が月額108,333円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある人は月額150,000円未満)を継続して超える場合は、当組合の被扶養者からは外れていただくことになります。
ただし、収入が上記の基準額以内で、かつパートタイマー先で健康保険に加入しない場合は被扶養者として継続できます。
事務所の事務担当者の方が行う手続き
当組合までご連絡ください。「事業所関係変更届」を送付しますので必要事項を記入の上ご提出ください。添付書類は不要です。
事業主の推薦を受け「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
退職・異動などで委員に変更が生じる場合は、「健康保険委員・健康管理委員 台帳」をご提出ください。
当組合までご連絡ください。
届け出
健康保険を使用することはできません。仕事中や通勤途中に負ったけがについては、労災保険をご利用ください。負傷された方自身が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず労災保険へ手続きを行っていただくことが必要となります。
通勤災害による病気・けがが労災保険の給付対象として認められるのは次のような場合です。
-
仕事との関連がある。
-
自宅と通勤地の往復である。
-
合理的は通勤経路・方法である。
-
往復の経路から外れたり、中断したりしていない。
通勤途上で日常生活上の活用をたすなどして通勤が短時間中断した場合は、中断の間を除いて通勤途上とされます。一方、パチンコやマージャン、飲酒などで通勤中断が長時間に及んだり、途中下車して通勤を長時間中断した場合などは、その時点から通勤とみなされなくなり、その間に起きた事故については健康保険の対象になります。
-
労災保険については、労働基準監督署または事業所ご担当者にお問い合わせください。
次のケースに該当する場合、保険給付の全部または一部について制限されます。
-
故意に事故を起こしたとき
-
喧嘩、泥酔により事故を起こしたとき
-
正当な理由なしに医師の指示に従わなかったとき
-
詐欺、その他不正の行為により、保険給付を受けたり、受けようとしたとき
-
健康保険組合が指示する念書の提出や質問などを拒んだとき
上記のケースに当てはまる事実が確認された場合、保険給付の全部または一部を行わないことがあります。
「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人が同意すれば医療機関がオンライン資格確認で自己負担限度額の区分を確認することができるため「限度額適用認定証」の申請は不要となります。医療機関にご確認ください。
「限度額適用認定証」が必要な場合は申請書に必要事項をご記入いただき郵送で当組合宛にご提出ください。
「健康保険限度額適用認定申請書」を当組合にご提出ください。内容確認後、当組合から申請書に記載された住所に送付いたします。
当組合に到着してから約1週間程度です。(特定記録で送付)
なお、被保険者の住所以外へ送付ご希望の場合は、申請書にその送付先をご記入ください。また、送付先を医療機関にされる方は、医療機関へ確認のうえ、必ず受取り対応してくれる方の部署名・氏名等と電話番号を記入してください。
当組合の限度額適用認定証は、申請のあった日(当組合受付日)の属する月の1日から最長で1年間を有効期限としております。(前月以前にさかのぼっての発行はできませんので、ご利用に間に合うようにご申請ください。)
有効期限後も限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請手続きをしてください。有効期限が切れた限度額適用認定証は当組合にご返却ください。
速やかに当組合へご返却ください。なお、以下に該当する場合についても、当組合へご返却ください。(紛失された場合は、滅失届のご提出が必要になります。)
-
資格を喪失したとき(退職、被扶養者削除など)
-
有効期限に達したとき
-
適用対象者が70歳になったとき
給付
当組合では事業所へ委任払いを行っております。申請時、事業所委任を指定されている場合、事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。
公金口座を指定されている場合、マイナポータルよりご自身の登録された口座をご確認ください。
当組合へ到着後、最短で1か月~1ヶ月半ほどでご指定の口座へお振込みをしております。内容不備・書類不足等で調査にお時間をいただく場合はこの限りではありませんのでご了承ください。
当組合では「傷病手当金」「出産育児一時金」「出産手当金」「埋葬料」に組合独自の付加給付があります。
-
但し、任意継続被保険者の方は「出産育児一時金」「埋葬料」のみ支給対象となります。
当組合には付加給付がございます。ご申請ください。
また、出産費用が法定給付の金額を下回っている場合、差額が発生いたします。付加給付とあわせてご申請ください。
夫婦が共働きでそれぞれに被保険者本人になっているときは、妻の加入している保険から被保険者本人として給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
出産育児一時金は母体を保護する目的のために、分娩の事実に基づき支給されるものなので、妊娠4か月(85日)以後の分娩であれば、生産、死産、早産のいずれを問わず、給付の対象となります。
両方の健保からの給付はできません。出産した病院と交わした合意文書に記載された健保へ請求をしてください。
請求できます。
申請ごとに内容を審査したうえで支給決定を行います。申請書の内容から、療養のため労務不能と認めることができない場合など要件に該当せず支給されない場合もあります。(申請期間を経過した事後の申請になります。事前申請ではありません。)
a. 就労時間中に業務災害以外の事由で発生した傷病について労務不能となったときは、原則としてその日を待期の初日として、待期期間中に算入されてその起算日となります。また、就労時間終了後に労務不能となったときは、その翌日から起算します。
b. 療養のため欠勤開始の日から3日間が年次有給休暇の取扱でも、その3日間をもって待期は完成します。また、療養の開始日および待期期間中に公休日(土曜・日曜・祝日)が含まれていても待期期間に算入され待期が完成することになります。
短時間でも就労した場合、その日は支給の対象となりません。
内容を審査した結果、決定通知書を申請書に記載されているご住所にお送りします。通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
同一の疾病で厚生年金保険法の障害厚生年金または障害手当金をうけられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金または障害手当の額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額を支給します。(健康保険法第108条第3項、第4項)
申請期間が在職中のものであれば、手続きが退職後であっても申請できます。退職日までの事業主の証明が必要ですので、会社を通じてお早めにお手続きください。
被保険者死亡後の傷病手当金は、法定相続人からの申請が必要になります。戸籍等を添付していただく必要がございます。
詳しくは当組合給付グループまでお問い合わせください。
労務不能であっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
健康保険を使用することはできません。仕事中や通勤途中に負ったけがについては、労災保険をご利用ください。負傷された方自身が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず労災保険へ手続きを行っていただくことが必要となります。
次のケースに該当する場合、保険給付の全部または一部について制限されます。
-
故意に事故を起こしたとき
-
喧嘩、泥酔により事故を起こしたとき
-
正当な理由なしに医師の指示に従わなかったとき
-
詐欺、その他不正の行為により、保険給付を受けたり、受けようとしたとき
-
健康保険組合が指示する念書の提出や質問などを拒んだとき
上記のケースに当てはまる事実が確認された場合、保険給付の全部または一部を行わないことがあります。
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがによりその支給がはじめられた日から起算して1年6ヶ月となっています。日数が残っていれば受給可能です。
なお、法定期間満了後に同一の病気により労務不能となった場合、傷病手当金を受給することはできません。
現実に支給を開始した日が、傷病手当金の支給期間の起算日になります。傷病手当金は療養のため仕事に就くことができないときに第4日目から支給されますので、3日間の待期期間を完成させ第4日目も労務不能であれば第4日目から支給され、その日が支給を開始したにとして起算日になります。
-
但し、給与等が傷病手当金の日額より上回り傷病手当金が支給されなかった場合、起算日は現実に支給を開始した日になります。
被保険者や被扶養者が、海外旅行や海外勤務中に業務外の病気やけがをしたときには、現地の医療機関では日本の健康保険は使えません。そのため、いったん立て替えて支払っていただき、健康保険組合に申請し、払い戻しを受けることとなります。ただし、やむを得ないと認められない場合(治療目的の渡航等)には医療費の給付はされません。
支給額は、国内での健康保険法の基準によって算定された額になります。海外での治療内容や医療費は国によって異なるため、実際の給付額は、支払った額(支払い総額から自己負担相当額を差し引いた額)より大幅に少なくなることがあります。支給の算定に用いる換算率は、支給決定日の外国為替換算率となります。
押印されていない場合、海外渡航期間が確認できる航空券のコピー(eチケットの控え含む)やマイレージ記録等を提出してください。
治療目的での渡航は海外療養費の対象にはなりません。
出産予定日より早く出産した場合、出産日を基準に産前産後の期間を計算することになります。
別々での申請も可能です。
産前分は出産後に、産後分は産後56日以降に申請してください。
ただし、医師証明はそれぞれの申請ごとに必要となります。
移送費は以下の1. から3. の要件のすべてを満たしていないと支給されません。
-
移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
-
患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること。
-
緊急その他やむを得ないこと。
1. と2. に該当していても、3. の緊急性が認められない場合、支給対象とはなりません。
「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人が同意すれば医療機関がオンライン資格確認で自己負担限度額の区分を確認することができるため「限度額適用認定証」の申請は不要となります。医療機関にご確認ください。
「限度額適用認定証」が必要な場合は申請書に必要事項をご記入いただき郵送で当組合宛にご提出ください。
当組合は高額療養費は自動払いとなっているため申請の手続きは不要です。 医療機関等から届く明細書をもとに高額療養費の支給決定を行い、その通知書を事業所宛に送付します。
高額療養費に該当する場合、受診月より概ね3か月程度で事業所の給付金口座に振り込みとなります。事業所の給付口座に振り込み後、事業所より被保険者へ支給となります。また、医療機関からの請求の遅延等により、支給決定に大幅に時間がかかることがあります。
高額療養費は、保険点数(厚労省が定めた診療報酬点数表に基づいて算定する)に基づいて計算をし高額療養費として支給されます。
よって、自費診療、差額ベッド代、食事療養は高額療養費の対象とはなりません。
健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途中以外のものであれば、その死因は問われません。
なお、交通事故等の第三者行為により死亡された場合、「第三者の行為による傷病事故届」をご提出ください。相手方から賠償を受けられる場合、お支払いできないことがございますので当組合にお問い合わせください。
被保険者が資格喪失後となる場合、家族埋葬料は支給対象にはなりません。
葬儀代はもちろんですが、そのほか霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。(参列者の接待費用や香典返しなどは含まれません)
やむを得ない事情で医療費の全額を負担した場合、後で被保険者が当組合に請求することにより、療養費として払い戻しを受けられる場合があります。健康保険適用分を算定した金額で計算し、自己負担額を除いた金額を払い戻します。健康保険適用外分や消費税などは支給対象とはなりませんのでご了承ください。
当組合加入後の期間の受診については、療養費(立替払い)をご申請ください。
なお、自己負担限度額や負担割合が異なる場合、返金した全額が払い戻されない場合があります。
臍帯血や骨髄液、臓器移植の運搬費用は「療養費(立替)」でご申請ください。
詳しくは組合給付グループまでお問い合わせください。
9歳未満(8歳まで)の小児が眼鏡を作成した場合、「弱視」「斜視」「先天白内障術後の屈折矯正」の治療用眼鏡であれば健康保険の支給対象となります。療養費(治療用装具)としてご申請ください。該当するかどうか審査を行います。
請求できます。
給付対象は下記の通りです。
-
鼠径部、骨盤部もしくは腋窩部のリンパ節郭清術を伴なう悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢リンパ浮腫について、医師が弾性着衣および弾性包帯の装着の必要を認め、医師の指示によりこれらの弾性着衣等を購入したときの費用。
-
慢性静脈不全による軟磁性腫瘍について、医師が弾性ストッキングおよび弾性包帯の装着の必要を認め、医師の指示によりこれらの弾性着衣等を購入した時の費用。
2個目は対象になりません。
オプションは支給対象になりません。
あくまでも「レンズ」「フレーム」のみが支給対象となります。
2足目は対象になりません。治療上の必要性から作製した装具が支給対象になります。また、耐用年数内は破損しても修理して使用することが原則です。そのため、洗い替えなどの日常生活の利便性のためや、スポーツをするときなどの一時的な使用を目的として作製された2個目以上の装具については支給対象になりません。
治療用装具の使用目的は「治療段階における症状の回復および改善」であるのに対して、補装具の使用目的は「おもに症状固定後の日常生活の補装具」です。
補装具は療養費の対象とはなりません。
健康診断
設計Infoのアカウント未取得の場合は、「生活習慣病予防健診のご案内」記載のQRコードや当組合HPより、アカウント作成をお願いいたします。Web問診のメール送信のタイミングは受診日の約1週間前と、3日前です。メールが受信できなかった場合はご自身で設計Infoにログインしていただき、問診入力をしていただきますようお願いいたします。
当組合健康診断センター受診の方は、設計Infoより健診結果をPDFで確認することが可能です。
健診受診日の約1週間前から入力可能です。
健診予約後に送付している「生活習慣病予防健診のご案内」に記載されているQRコード「健診の内容についてはこちらから」よりご確認ください。
受診日の変更をお勧めいたします。詳しくは健診予約後に送付している「生活習慣病予防健診のご案内」に記載されているQRコード「健診の内容についてはこちらから」よりご確認ください。
50歳~70歳までの年度年齢が偶数の方は胃部X線から変更することが可能です。ただし、検査日は別日となります。当日、内科診察時に医師に変更の旨をお申し出ください。
Web問診のオプション検査項目にチェックをしてください。費用は当日窓口にてお支払いください。
被保険者・被扶養配偶者・被扶養家族(40歳~74歳)の方は所定のコースが無料です。オプション検査につきましては自己負担となります。
委託健診機関一覧表を確認し、直接希望する委託機関へ電話にて予約してください。
40歳以上の方は東振協Bコース、40歳未満の方はA2コースがございます。女性健診ご希望の場合は、女性健診も一緒に受診したい旨をお伝えください。
(社)東振協を通して他健保組合との共同事業となりますので、締切後の追加申込については、対応できません。
(社)東振協へ直接お電話にてご連絡をお願いします。
施設利用
組合員専用ポータルサイト「設計Info」から、抽選申込・空室申込ができます。
希望日の1か月前の同日午前10時から、電話にて受付します。土曜・祝前日(休日料金)のご利用については、希望日の2週間前の午前10時から電話にて受付します。いずれも該当する日が組合休業日の場合は翌平日から受付します。
利用日の前日の正午まで組合健康企画グループでお受けします。ただし、利用日の前日が組合休業日(土・日・祝日および年末年始等)の場合は、現地へ直接ご連絡ください。
ご利用日前日の正午を過ぎてからの取消や変更につきましては、キャンセル料金として宿泊料金全額を申し受けます。
利用希望日の3か月前(祝日の場合は翌日)から電話にて予約を受付けます。
(例)6月5日にご利用を希望 → 3月5日より受付
予約が取れましたら「利用申込書」に必要事項をご記入いただき、当組合へご提出ください。
机と椅子をすべて並べた状態で最大60名様でのご利用が可能です。
健康管理・各種補助金
①領収書原本…領収書の宛名は、被保険者・被扶養者のフルネームに限ります。
②宿泊証明書…申請する方全員の氏名が記載されたもの。
これらの書類が必要となります。
令和6年度(令和7年3月31日宿泊分まで)の申請は、事業所担当者様を通じて申請書類を郵送にてご提出ください。
令和7年度(令和7年4月1日宿泊分から)の申請は、被保険者様ごとに「リロクラブ(福利厚生倶楽部)」組合員専用サイトにてWeb申請してください。
①チケット購入時の領収書
②Webチケット
③クレジット決済(写し)
④予約完了メール(写し)
①~④の中で次の必須項目すべてを網羅する書類が必要となります。※組み合わせ可
・申請者氏名(被保険者または被扶養者)
・利用日
・金額(単価)
・人数(枚数)
・区分(大人・小人)
被保険者様ごとに「リロクラブ(福利厚生倶楽部)」組合員専用サイトからWeb申請してください。
被扶養者様の分の申請も被保険者様が代表して申請してください。
組合HPの「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券について」から、Googleフォームまたは郵送にてお申し込みください。
令和7年6月1日~令和8年3月31日です。