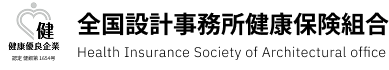生活習慣病予防のポイント
生活習慣病を予防するために、日常生活を見直しましょう。
生活習慣病とは、主に生活習慣(運動、食習慣、飲酒、喫煙、休養等)が原因になって発症する病気です。肥満、高血圧、糖尿病、脂質代謝異常、肝機能障害、脂肪肝、高尿酸血症(痛風)、メタボリックシンドローム(※)、癌などがあてはまります。
-
メタボリックシンドロームとは、内蔵型肥満に高血圧、高血糖、脂質代謝異常のうち2つ以上が合併した状態をさします。改善には肥満を解消することがもっとも有効です。
Check! ~まずはこちらの確認を~
-
食事量・バランスに注意
-
腹八分目を心がけ、ゆっくり噛んで食べる。
-
主食、主菜、副菜をそろえた定食形式をとる。
-
-
「規則的な食事を」「朝食をとる」
-
1日3食とし、夜は少なめを心がける。
-
欠食をしない。
-
-
野菜を食べる
-
野菜は1日350g(小鉢5皿分)が目安。
-
色の濃い野菜と薄い野菜を合わせて選ぶ。
-
-
外食では小鉢を追加したり、彩り良いメニューを選ぶ。
-
その他に海藻、茸類をとる。
-
-
お酒は適量に
-
休肝日を週2日設ける。
-
1回の飲酒量はビールなら500ml(ロング缶1本)、日本酒なら1合、焼酎ならコップ半分、ワインならグラス2杯、ウィスキーならダブル1杯にとどめる。
-
-
適度な運動を
-
毎日の生活で1000歩増やす。
-
歩く速度をアップする。
-
ダンベルや腹筋など筋力アップする。
-
(基礎代謝が高まり太りにくい体になる)
-
-
-
禁煙に挑戦
-
タバコの有害成分が血管壁を傷つけ、動脈硬化を促進する。
-
禁断症状を乗り切るために歯磨きやお茶を飲む。ニコチン依存度が高い方は禁煙補助剤等の利用を検討する。
-
-
-
ストレスをためない
-
休養・睡眠をとる。非日常の時間をもつ、愚痴をきいてもらう等の対処法をもつ。
-
(ストレスは血管収縮させたり血圧や血糖を上げるホルモンを分泌し病気の引き金になる。)
-
-
-
睡眠不足に注意を
-
疲労回復、免疫力アップのためには1日6~7時間は最低確保する。睡眠が足りないときは、通勤時や昼休みに15分程でも仮眠をとる。
-
日常生活のアドバイスをもとに、詳しくみてみると...
毎日決まった時間に体重を測定しましょう。3~6ヶ月で体重の5%減量が目安です。
体脂肪燃焼には息がはずむ程度の運動を毎日するのが理想です。
家庭での安静時血圧を測定しましょう。早朝空腹時と就寝前の2回が理想です。
運動により血圧を下げるホルモンの分泌が促されます。激しい運動は逆効果です。
佃煮や漬物を控える、麺類や味噌汁の汁は残す等に注意し、薄味を心がけましょう。
これらの食品に多いカリウムは血圧上昇を抑制します。毎日とりましょう。
定食形式の食事を心がけ、鉄分の多い赤身肉、レバー、まぐろやかつお等の魚、貝類、大豆製品、青菜、ひじき等をとりましょう。
野菜、海藻、茸類には血糖の急激な上昇を抑制する働きがあります。毎食取りましょう。
適度な運動を継続することでインスリンが活性化され、血糖値を下がりやすくします。
青魚を増やし、脂肪の多い肉、乳製品の取りすぎに注意しましょう。
卵黄や内臓類の過剰摂取を避けるようにしましょう。
運動によりHDLコレステロール(善玉コレステロール)が増え中性脂肪が減ります。
主食や果物、菓子、お酒等のとり過ぎで中性脂肪は上昇します。特に夜間は控えましょう。
野菜、海藻、茸、未精製の穀類等の食物繊維をしっかりとると血中脂質改善が期待できます。
大量飲酒はアルコール性肝炎や脂肪肝の原因に。少量飲酒でも高値なら節酒(禁酒)しましょう。
お酒を飲まない方で高値の方は体重増加が原因になることがあります。減量しましょう。
1日2リットルを目安にお茶や無糖飲料でとりましょう。尿酸排泄を促します。
運動による内臓肥満の是正により尿酸値は改善します。
肝臓や白子、干物などやビールに多く含まれます。
血清尿酸値を上昇させるので飲み過ぎないようしましょう。
保健師・管理栄養士の健康相談をご利用ください
一人一人にあった健康をサポートします。健診結果の見方、具体的な減量方法、禁煙相談、食事分析などお気軽にご相談ください。生活改善に役立つ資料もご提供できます。
生活習慣と健康

リロクラブ(福利厚生倶楽部)のご案内
組合員の皆さまの健康増進・更なる保健事業の拡充を目的に、株式会社リロクラブと提携し提供したサービス「リロクラブ(福利厚生倶楽部)」をご利用いただけます。
健康、リゾート、レジャー、エンタメなど、約350万種の様々なメニューを、組合員特別価格でご提供。ぜひライフスタイルに合わせてぜひご活用ください。